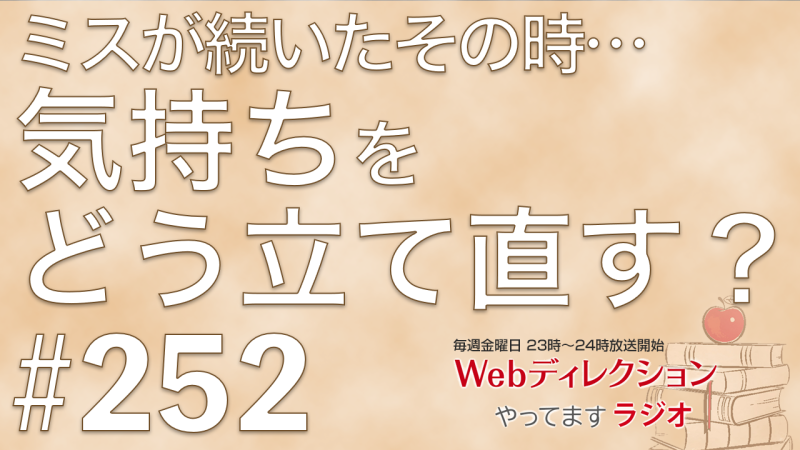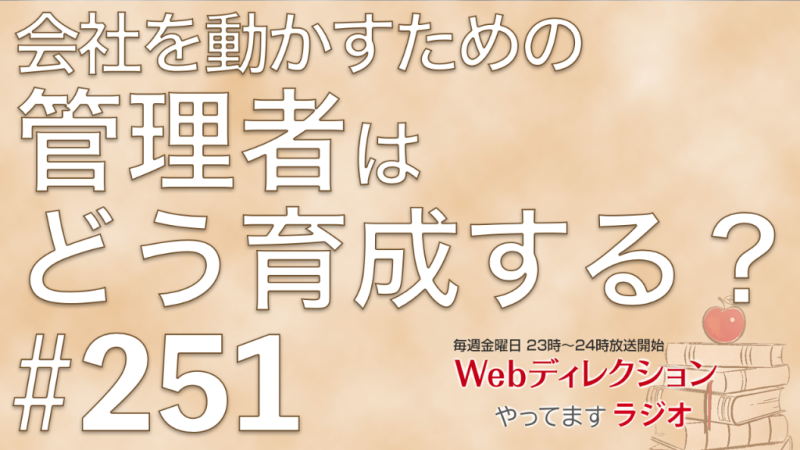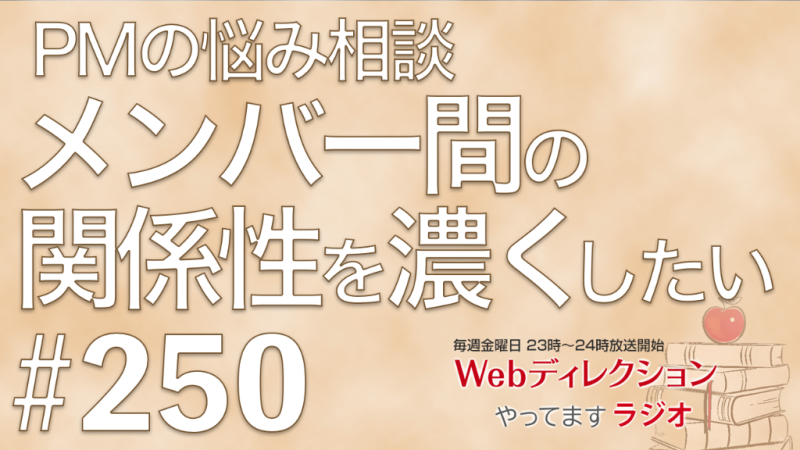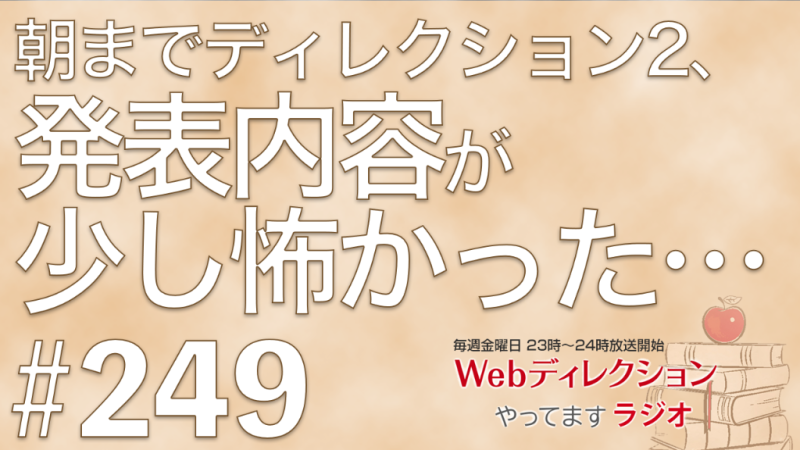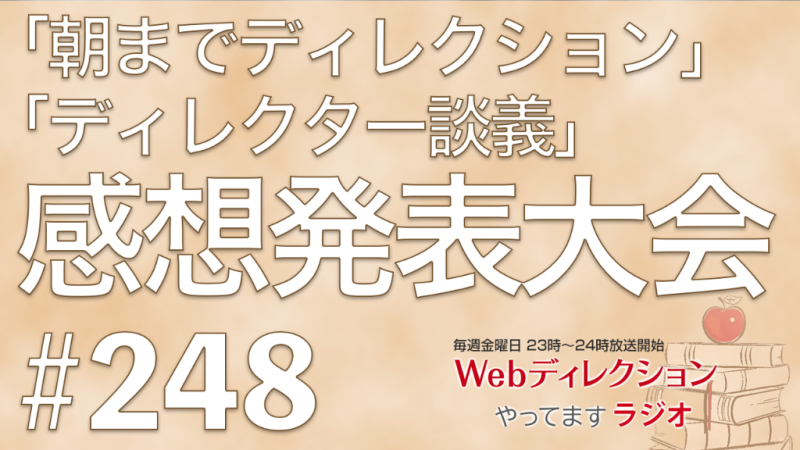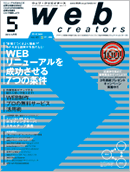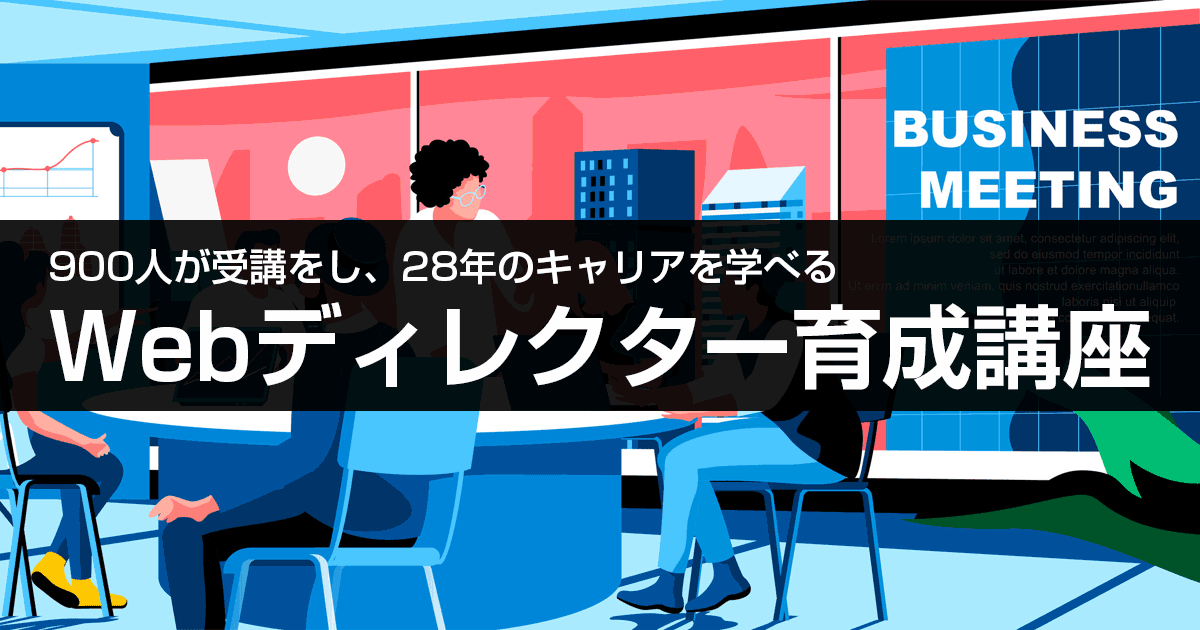動画をどう扱っていくか?
2006年10月29日
CGMって言葉が生まれて久しいですが、これから全部が全部ではないにしろ、ますます企業サイトは個人の展開していくサイトと競合していく部分が生まれてくると思います。
なぜならやっぱり「Webは楽しくなくちゃ面白くない」っていう思想が根底にあるからだろうと思います。
90年代に名村を含むインターネット草創期のメンバーというのはやっぱり「Webサイトを見るのが楽しかった」んだと思います。
だから実際にはそのサービスに興味があろうと無かろうとWebサーフィンをしていた訳です。
先日ふとYouTubeで見つけたこの動画をみて、そんな事を思い出していました。
エレキギターだけでここまで見せる人ってのもなかなか居ないとは思いますが、これは冷静に見れば、構成も画質も音質も決して言い訳ではない。
ただひたすらコンテンツの面白さだけで3分も人を見せているわけです。
声優の業界では「下手なナレーションは1分たりとも聞きたくない。耳が腐る」と言われたりしていました(笑)
それは余談ですが、これからますます「Webってやっぱり楽しいよね」といった部分をブランド価値に付与していく、もっと言えばそのサービスに「面白さ」というのを付加価値として追加していかないと、エンドユーザーのますます肥えてくる感覚には耐えられなくなってくる。
その意味ではサービスの提供手段や提供基準のドラスティックな過渡期にいるのかもしれませんね。
お金をかけるわけではなく、コンテンツの面白さを追求するには、ますます頭を使い、エンドユーザーを未定かなければなりません。
企業が企業の言葉で何かを伝える時代は遠からず、衰退していくと思います。
そんな話は明日のセミナーなんぞで話したりするかもしれませんが[謎]
当日でもお待ちしています(笑)