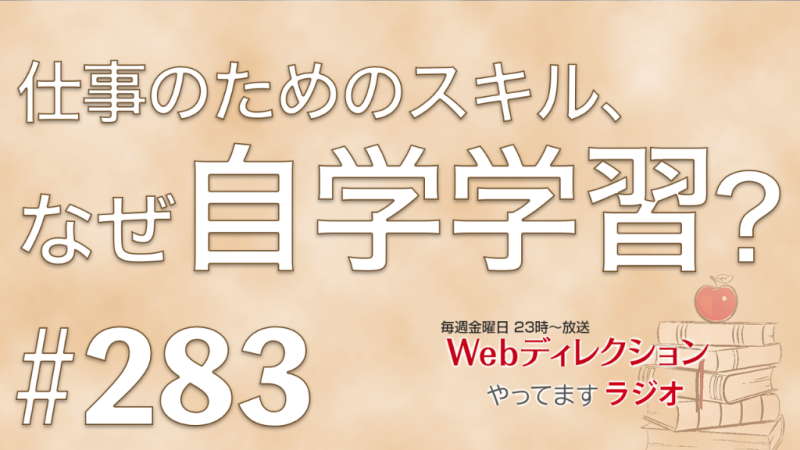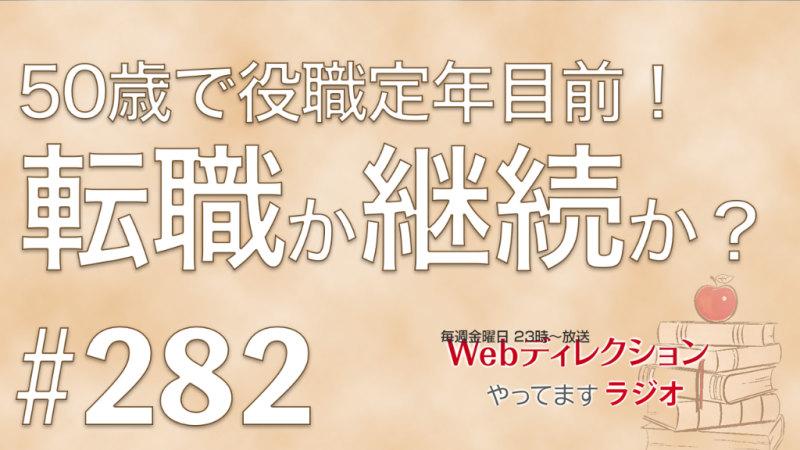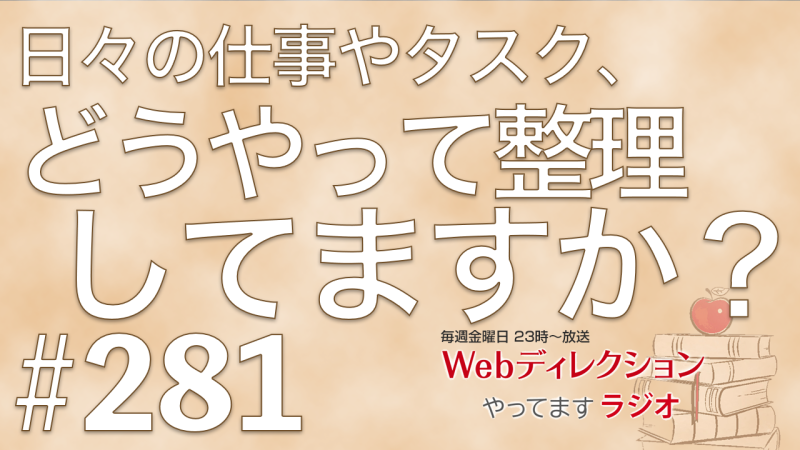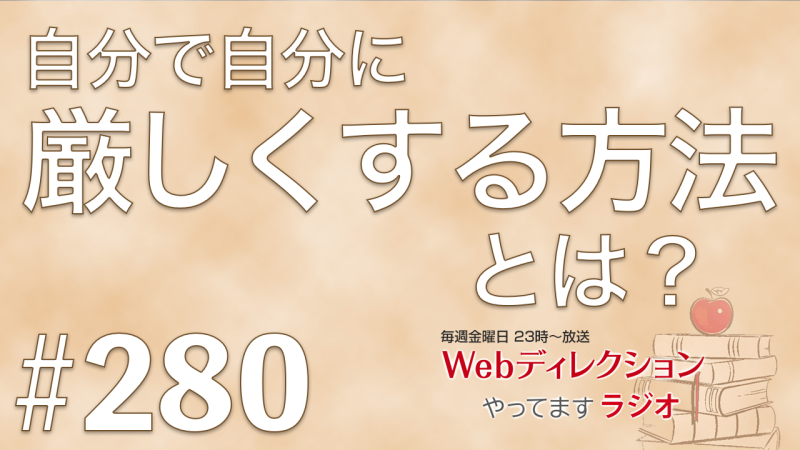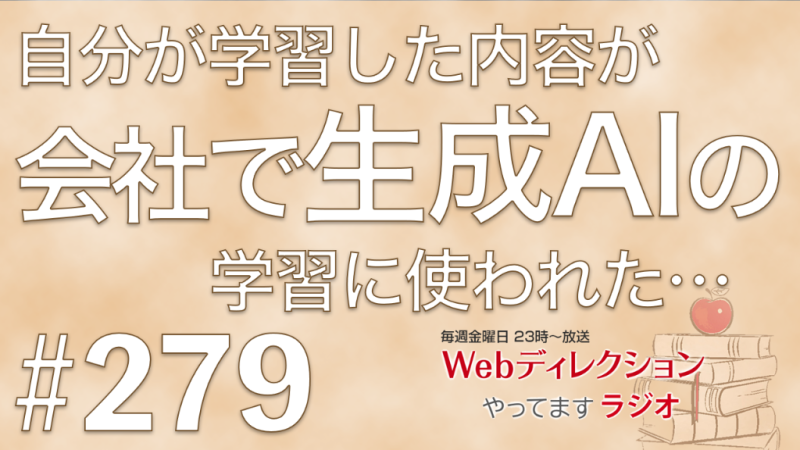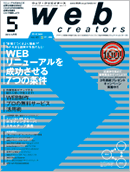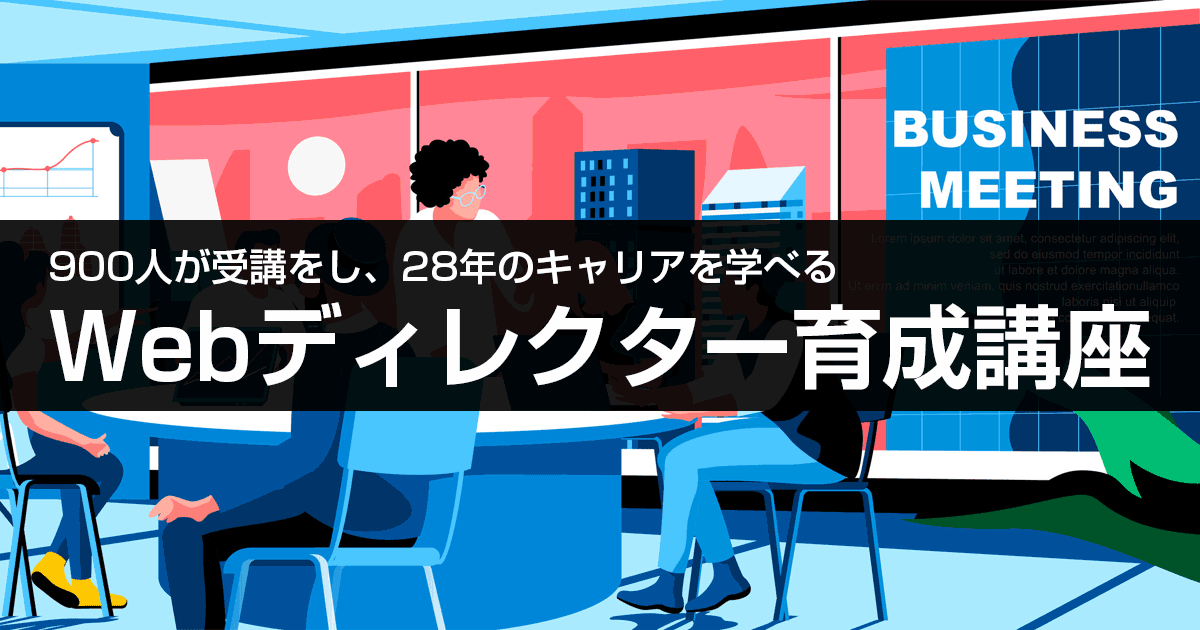働き方の揺り戻しが始まった
2025年10月06日
2025年10月の自民党新総裁選挙で高市さんが選ばれ、その際「ライフワークバランスを捨てる」と発言されました。
このことはSNSでもいろいろな意見が出ていますが、個人的にはこの言葉を政治関係者が発言したことはとても大きい潮流の変化だと感じました。
戦後から続いていた猛烈な働き方を経て、2000年頃からはそれを抑制する動きになりました。もちろんそこには過労死や精神的な疾患などが世間的に顕在化したという世情もあります。。
しかし、その結果として誰しもが「無理して働かない」「競争社会は良くない」「お金を稼ぐだけが全てではない」…などなどいろいろなそれまでの『働くべし』という価値観へのアンチテーゼという価値観が生まれてきました。
ただ、そこから2025年に至るまでに「経済的な視点」に限っていえば、グローバルにおける競争力の低下、GDPが追い抜かれる、先端技術関連の多くで日本が勝てない状況になる…ということが起こりました。
「失われた30年」という言葉が生まれ、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』は、はるか昔の話です。
結果として国内では「なんで日本は生産性が低いんだ?」「物価が上がっているのに給料が上がらない」などなどの不満がたまった時代になっていたと思います。
「仕事」という観点においては、資本主義においては基本的には競争社会です(資本主義の是非は別として)。どこまで行っても優勝劣敗ですし、適者生存です。
つまりは「他社(他者)との比較」の中で競う必要がありますし、人類は経済的な部分だけではなくあらゆる面において「よりよいものを目指す」ことで太古より進化してきたと思います。
となると、実際「そこそこでいい」「頑張らなくていい」という感覚では「他社(他者)がより頑張っていれば」競争には絶対に勝てないし、「失われた30年」の後半は「頑張らなくていい」という風潮の結果ではないのかと思ってます。
日本がそういった価値観になっている期間に、方法の是非は別にしてアメリカも中国も頑張っていたわけです。アメリカに差を広げられ、中国に追い抜かれたのは、単純に『彼らがやっていたことを日本はやっていなかったから』だけだと思います。
「頑張ること」を拒否し続け、この国際的な状況に甘んじ、給料が上がらず、国際的な競争力が下がり、国際比較の中で人件費が安い国となり「製造業における安価に作れる国」という国を目指すならば、それでもいいかもしれません(要は20年ぐらい前の中国や東南アジア諸国のような状況)。
様々な価値観を全部考慮して守るのは不可能になってきた
よく「質より量」ということが言われますが、『考えた上で』とか『無意味にやるのは無駄』という言葉が先行していて、それ自体は正しいけど、ではそれらをクリアした上で、『熟慮をして意味ある行動と思われることを実際にしていた人』はどれぐらいいたのでしょうか。
こういった「Aをするべき」という話題になると「いや、Bの観点を無視してやるべきでない」「Cの観点を無視してやってどうするの?」という意見が必ず出ます。
冒頭の高市さんの「ライフワークバランスを捨てる」というセリフにもそういった意見が出ていました。
- ライフワークバランスを無視したらまた過労◯する人が出てくるがそれを助長するのか?
- 国会議員としてもっと違う言葉の選び方があったんじゃないか?
- 自分以外にもそれを強要するのは総裁としてどうなのか?
などなどです。
「ライフワークバランス」という言葉だけを取り上げるならば、ある意味においては正しいかもしれません。
しかしあのスピーチは少なくとも私は「総裁としての覚悟であり、失われた30年を取り戻すためにはそこまでやらないといけない。『適度なバランスを取る』といったお為ごかしをいっていてどうにかなる時代ではない」ことを言語化したものだと感じました。
その言葉の結果として国政がどうなるかは今後の話です。今の時点で評価するべきでもありません。
『有言不実行』だったら総裁や国会議員から落とされ、最悪無職になるのですから。逆にいえばその可能性がある以上、国会議員はちゃんとリスクテイクをしていると思っています。
また「言葉の選び方」についても、いくら国会議員でも人の子です。あらゆる方面に100%リスクヘッジをした言葉でフリートークができることを求めるべきではないと思います。「国会議員になるということは、そのケアもできて当然だ」というような声が聞こえてきそうですが、それは誰もそんな定義をしていないので、勝手な解釈で他者に責任を強制するべきではないと思っています。
逆にそれを求めるならば、全ては準備した原稿を読むしかなくなります。
仮にそれをしたら次には「原稿を読んでばかりで◯◯さんの人として部分が見えないつまらない人だ」「原稿がないと何も喋れない人だ」みたいなことをいう人が出てくるわけですから。
ですので、『どういうことをしても文句を言う人はいる』という前提に立つならば、あのセリフを自民党総裁が発言したことの意味は「時代の転換点」の象徴なのではないかと感じています。
何度もいいますが、「その言葉を発した結果は今後で判断する」ので、今の時点で政治手腕を評価するとかの意図は全くありません。
易きに流れていく世論には歯止めが効かなくなる
僕はいまも自分が30代のころと同じ様な働き方をしているつもりです。
よく周りからは「若くないんだから無理しない方がいいよ」といわれたりしますし、それも理解しています。
ただ、無理にでもそういった働き方を維持しているのは「易きに流れ、気力と体力が落ちるのを防ぐ」意味あいが大きいです。(単純に労働時間が長い、というだけですが)
今後、絶対に体力は低下します。体力が低下すると連動するかのように気力や感受性も低下していきます。
それ自体はもう抗えない事象なのですが、だからといって簡単に「もう40代だから…」「50代になったんだし…」という言い訳を自分にすると、時代がまたシャカリキに働くことを求めることになった時、その流れに付いていけなくなります。その時に脱落することへの怖さから「意地でも現状維持をする」というのが今の自分の働き方の大きな要因です。
体力が落ち、安穏とした仕事の仕方に身体も気持ちも慣れてしまうと、「今はここ一番、体力を振り絞って頑張らないとまずい!」みたいな時に踏ん張りが効かなくなってしまうはずなんです。
一昔前、「ゆとり教育」が無かったことにされましたが、ではその「ゆとり教育」世代の人が「今までの常識はユル過ぎたので元に戻します!」と世間にいわれ、翌日から彼らにとっては前時代的な仕組みややり方に戻されたとして即応できるか?といえば(多くの場合)不可能だったのではないでしょうか?
その意味では1975年前後の生まれのいわゆる「就職氷河期世代」、私自身がまさにそうですが、この世代は今に至るまでいろいろ言われていますが、僕には「ゆとり世代における『ゆとり撤廃後』」もなかなかハードモードなんじゃないかと思っています。
ですが、その「ゆとり時代」の真っ只中はどうだったでしょうか?
世間一般ではゆとり教育はそれまでの「詰め込み教育へのアンチテーゼ」のように称賛されていました。
そしてその風潮に同意した人もたくさんいました。「これからの教育とはこうあるべきだ!」と。
なぜならそっちの方が全体的に「楽」だから。
人は意識をしなければ必ず「楽」に流れていきます。群衆心理がその「楽」な方に向かえば、なおさらその風潮に歯止めが効かなくなります。その意見単体に対して「いいか?わるいか?」でいえば「悪い」と否定のしようがないのです。
本来勘案するべきは「その結果としてどうなるのだろうか?グッドケースとバッドケース、どちらも起こり得るが、仮にバッドケースになった場合に対応できるのか?」という点なはずなのに、です。
そして「目の前の楽」に同意するほうがさらに「楽」なので、それに反する動き・考え方・意見は社会悪になっていきます。
これはその渦中は別に構わないかもしれません。なぜなら世間の大多数がそれを「よしとしている」のですから。
さらにそれに従わない意見は徹底的に叩かれて潰されるので、日本のいじめ問題のように「違う意見だったとしても言わない方が悪目立ちして叩かれないから良い」わけです。
と書くと、僕にも「今まで言ってこなくて、今回言うならもっと早く言っておけばいいじゃないか」と思われるとおもいますが、『わざわざ波風を立てるメリットが僕になかったから言わなかった』というのが本心です。
揺り戻しが起こった時に耐えられる自分であるか?
問題なのは、この流れが変わった時です。
例えば今の日本ではインフレがつき進んでいます。しかし給料は上がらない、という状況に多くの問題が指摘されています。
ですが、今現在の起こっている問題が発生するのでは?ということは、以前から考えていました。
これは過去にセミナーなどでも話題にしてお伝えしていたのですが、きっかけは2014年ごろに牛丼が250円になったときです。
牛丼の値段がどんどん安くなっていくのを見ていて、「これって今後…どうなるんだろ?」と思っていました。 どういうことかというと、今から25年前の2000年ごろは牛丼並盛は400円でした。 これが250円に向かってどんどん安くなっていく時、まだ若手でしたから確かにおサイフに嬉しかったです。
しかし、一方でこうも思いました。
「一体何をどう頑張れば400円の商品が250円になるのか…?」
考えれば簡単です。 どこかで必ず「値引き」をしているんです。
牛丼屋の仕入れ先→仕入れ先はその先の仕入元→……と続き、最後のどん詰まりまで等しく値引きを強いられていたはずです。
ということは途中を含めて最終的な生産者まで所得が減ります。薄利多売で一瞬は儲かったかもしれませんが、結果的に今は牛丼の値段は元に戻っているので、結局は250円という価格に耐えられなくなったということです。
生産者の所得が減れば彼らの消費は当然減ります。経済は全て循環しているので、生産者の消費が減れば、小売店の売上が下がり、その対策としてさらに値引きをして…という悪循環になるのは明らかです。
そしてこれは「低所得者」側にとって大きな問題をはらんでいます。
「高所得者」も「低所得者」も「安くなる」時には何も問題はありません。
しかしこれが『インフレ側』に回ったときに大変なことになるのです。それは『低所得者が買えなくなる』ことです。一方インフレになっても「高所得者」はまだ「買うことはできる」ので、問題は問題ですがそこまで騒がない。
これはまさに今起こっていることです。物価と給与の変化が完全に一致しているならば問題ないのですが、経済の循環にはいくつかのポイントがあるので、連動できたとしてもどうしてもタイムラグが出てきてしまいます。また産業単位ではそれが反映されないところも出てきます。
この「揺り戻し」が起こり、その変化が『過去に比べて厳しい方に戻った』ときに大問題が起こります……
働き方も同じ事が起こるのではないかと思っています。 「無理をしない」「できる範囲でやる」といった価値観では少なくとも国際的な競争の中では勝てなくなっている。全員ではないが、諸外国でそれなりの企業にはシャカリキになって働いている人は一定数います。
少なくとも私が2022-2024に大学院に行っていた時の同級生は「自分が日本支社長をしていたドイツ企業の本社マネジメント層は一日中働いていた。プライベートも無し、時差も関係無し、そのかわり給料はめっちゃ高い」と言っています。ただこれは実際の資料としては分母のn数が「1」の話題なので、統計的にはその事例で判断はできないと思っていますが、そういう人もいる、ということです。
シャカリキというのが「稼働時間」なのか「稼働密度」なのか「解雇を掛けた責任」なのかは色々ですので、単一なことは言えませんが、とにかく何かしらのリスクを取って働いている人がいる、ということです。
もちろん過労死的な方にいくのは絶対に避けるべきです。特に私は現在経営者ですので、それは少なくとも自社では徹底して避ける方針です。一方で2000年代の働き方が問題だったのは、以下の要因があるように感じています。
- 高度成長時代の名残で、会社員は個々人の能力を別にして一定の無理な働き方を強要された
- 個々人の頑張れる限界値というのを全く考慮していなかった
- IT化によって、90年代までの仕事の速度間や密度から一気に高速・高密度になった
これらのことからいわゆる『ブラックな労働の撤廃』に進み、2018年の「働き方改革」に至ったと思います。
また話題として「欧米のエグゼクティブクラスは◯◯をしている」という話題も危険な話だと思っています。一見正しそうなのですが、「それは何名の分母で何名の分子が◯◯をしているのか?」という割合が全くわからないからです。
「欧米の◯◯◯◯は」というのは、めちゃくちゃ曖昧な話なんです。「日本の社長は」と言っているのと同じで、上場・非上場関係なく、産業も会社規模も関係なく、一緒くたにまとめてしまっている。でも、なんとなく「へぇ、欧米ではそうなのか……」と思ってしまいがちな文脈になりがちです。
要は前述したように欧米のエグゼクティブでも、
- シャカリキになってワークをし続けていて、その内容にみあった価値を出している人
- 長時間のワークをしている訳ではないが、それに見合った価値を出している人
の両方が存在します。(両方とも対稼働に対しての価値をだしていることが前提です)
「長時間働くのは仕組み化できていないことだ」「社長が長く働いている会社はやばい」というようなもっともらしい言葉もありますが、「集中力が続いて長時間稼働ができるならば、他社に先んじることができる」と考えるが成長を考える企業のマネジメントレイヤーではないでしょうか?
少なくとも「そこそこの働き方で上場目指そう」という経営者には出会ったことがありません。
上場を目指していなくても、会社が生き残るためには競合他社に何かしらで勝たないといけない訳です。企業が生み出せる価値は「かける時間✕方法✕才能」で決まるので、時間の要素はどうしても掛け算に含まれてしまうのです。
そして時代は必ず「少し進化した過去のやり方に戻る」を一定周期で繰り返しています。2000年の頃のような環境ではないですが、そろそろ「令和版のシャカリキに働く環境への回帰」という時代が来るんじゃないか?と感じています。
では、その時に自分はその状況に耐えられる心身であるか?。
耐えられるようにするために、ずっとそういった時代での働き方をしてきました。もちろんそれは僕自身の身体の状態、精神の状態などを常に自分で細かくウォッチしてのことです。
心身両面での休息のあり方、運動の取り入れ方、仕事への向き合い方、趣味の持ち方、自分で自分のモチベーションを練り上げるなどなど、やれることはやってきました。
体力は確かに落ちましたし、身体も20代と比べればガタも来ているでしょう。 運動もそれらしい運動はなかなかできていないのが実際です。ですが、まだ身体は動きますし、目も老眼はきていません!
大病もせず、「がん」にもなっていません(ここしばらく毎年PET検査を受けています(笑))
今2000年のころに戻ると当時の100%ではないですが、90%ぐらいはできる自身があります。知識と経験は増えていてそれでカバーという訳ではなく、肉体や精神的にも、仮に揺り戻しがあったとしても耐えられる状態を作ってきたと思っていますから。
ですので、時代がどう変わろうとも『自分の中の基準』は下げてはいけないと思っています。なぜなら「厳しい」ほうに戻った時、楽に慣れてしまえば、世間の変化についていけなくなるからです。
若い人はまだ対応ができるかもしれません。
ですが『25年前の働き方』を知らない若い世代の人たちが、僕らおっさんから『もっとシャカリキに働いた方がいいよ』と言われても「老害がしんどい働き方を強要してくる」としか思えないでしょうし、そんな話を素直に聞けというのは無理でしょう。
実際僕らも若いときにはおっさんから無茶を言われ「そんなのは何十年前の話ですか、全く…」と心の中で絶叫していましたから。
また、仮に若い方々が聞き入れてくれたとしても、「何をどれぐらいやったらいいか分からない」以上、基準は「自分なりにやった」になり、結局は必要な基準に達せない可能性も高いです。
必要な基準に達することができる若手世代というのは、「世の中がシャカリキに働くのが『当たり前』になった後の人たち」だけだ。
それは「ゆとりに慣らされた世代」が「ゆとり終了直後から、それ以前の学習に戻る」というのが容易ではないのと同じです。
今後の時代では、第三者から個々人の働き方や生き方への細かな干渉……というのは確実に減っていくでしょう。
その結果として仮に「働き方の揺り戻し」がおこった時も、周りは『あーしろ』『こーしろ』というのは言わないと思います。なぜならそれを言うことが『その人への過負荷を強いる』ことになり「その結果の異常の責任が取れない」から。
となると、生き残るには『自分で自分に、楽ではなく、潰れることのない自分にとって適切な負荷をかける』ことになります。その負荷をかけるかかけないかは完全な自己責任。
安穏と生きていても誰も困りませんが、本人は「給料が物価上昇に耐えられないほど上がらない」「欲しい報酬が得られない」ということになるかもしれません。もちろんそれでも良い価値観の人もいるので、自身が納得できているならば必ずしも給料が上がらないことは悪ではありません。
重要なのは「二極化の時代」になっていくのでは?という点です。
- 仕事をしてガンガン成長して稼ぎたいのに法令的なキャップがあることでそれができない人は思う存分働ける(ただ心身の管理は自分で行う必要がある)
- ほどほどのワークでいい人もそれは尊重するし強要もしない。でも成長も給料もそこそこか、それ以下だよというのを納得してもらう
こうなった時、自分はどちらを目指すのかを選ぶ時代になっていくのではないでしょうか?一律で横並びに「こういう働き方をしましょう。前ならえ!」とさせられ、「出る杭は徹底して打ち付けてなかったことにする」のではなく、「やっている人は徹底してやっていく」。
これは富の二極化を引き起こすので、実際には中間層が多い方がいいのですが、「一億総中流」と言われたのは1970年代ですから、今から50年も昔の話です。いま中間層を増やすことは難しいでしょう。
その解決は税制の話なのでここでは取り上げないですが、少なくとも流れとしの二極化に進み始めたと思っています。
こういう流れの中でもっとも大変なのは「安穏とした状態に慣れてしまい、シャカリキに働こうと思っているのに、気力も体力も落ち切ってしまい、今さらどうやっても戻れない」人です。
40歳後半以降ぐらいで、今からシャカリキに頭も身体もフル回転で働かなきゃいけなくなった時についてこられないで脱落する人が多数出てきてしまうのではないかと感じています。
しかし社会は優勝劣敗、適者生存なので、適応できないと一定のラインからは撤退するしかなくなってしまいます。
だからこそ生き残れるように爪を研いでおく必要があると感じています。
今回の自民党新総裁の言葉が発せられたことで感じている時代の転換点と揺り戻しが起こったときに耐えられる自分でいるか?と考えていたことが現実になったかも……と思っていることを文字にしてみました。